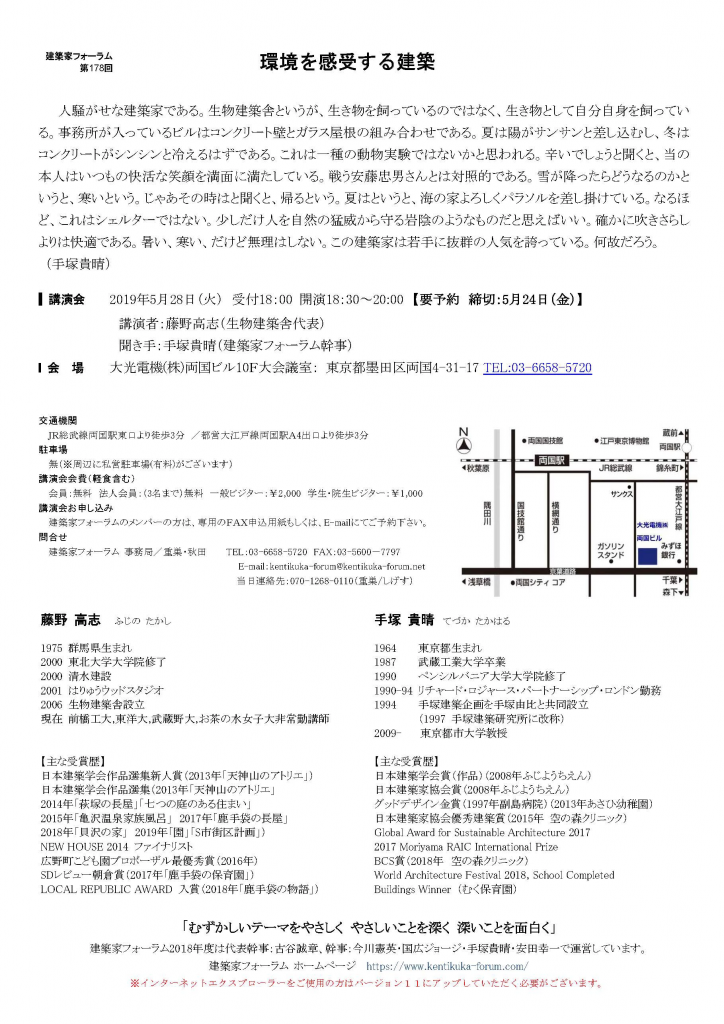【第178回(2019/5/28)】「環境を感受する建築」

建築家、藤野高志氏の事務所の名称は、「生物建築舎」と一風変わっている。聞き手の建築家フォーラム幹事、手塚貴晴氏の告知のコメントにはこうある。「生き物を飼っているのではなく、生き物として自分自身を飼っている。事務所として入っているビルは、コンクリート壁とガラス屋根の組み合わせである。夏は陽射しがさんさんと差し込むし、冬はコンクリートがシンシンと冷えるはずである。これは一種の動物実験ではないかと思われる」。藤野氏がつくった建物はいずれも環境と中にいる人間をがっちりと閉ざすものではなく、最低限の快適さを保ちながら、あくまでも周囲の環境を感受するものになっているようだ。
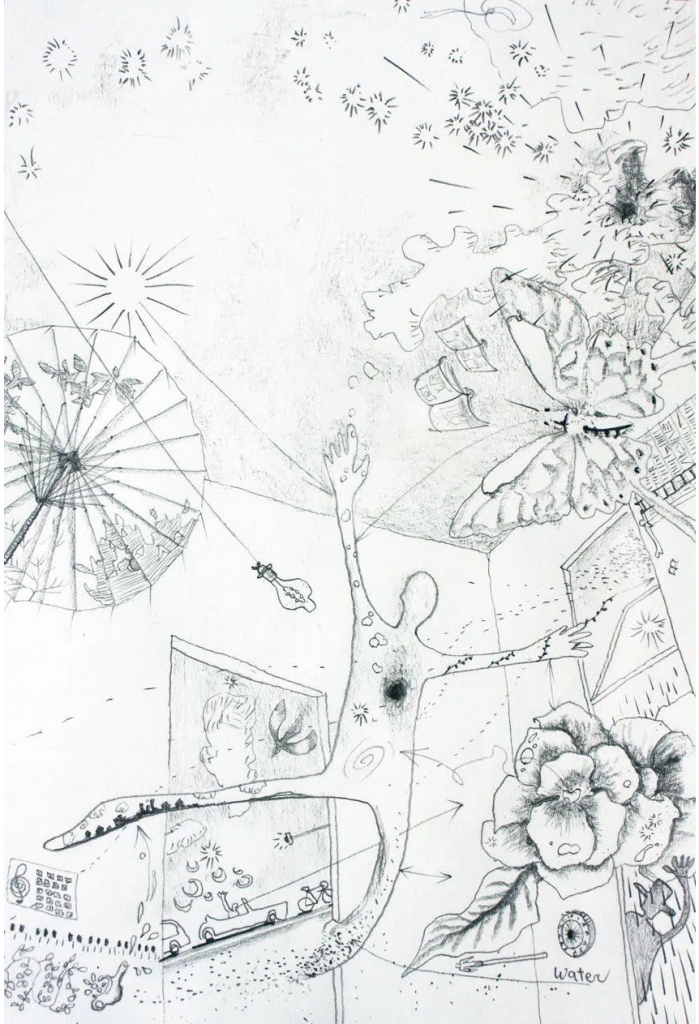
群馬県高崎市にある生物建築舎の事務所、「天神山のアトリエ」は、2011年の竣工当初は藤野氏の住宅兼事務所だった。幹線道路沿いに建ち、人目を引く不思議な不定形だ。180㎜の壁厚のコンクリート造のワンルームで、大きく切り取られた天窓、ハイサイドライトを通じ周囲の環境と室内が一体化したかのようだ。室内にいながら、晴れの日の青空はもちろん、夕立の豪雨と雷、降り積もる雪を体感できる。夜ともなれば室内の壁面には、車のヘッドライトに照らされた植物の影が巡る。室内に植えたレモンユーカリが成長しても支障がないよう、壁の最高高さは約8mもある。建物の内外とも地面に真砂土が敷き詰められ、人が歩くエリアはセメントを混ぜて突き固めているのだという。室内外に植わっているユーカリなど、のべ140種類の植物は植栽家の太田敦雄氏によるデザインで、見て楽しむだけでなく、場所ごとの空間の機能に合わせて異なる香りが設定されている。想像するに、事務所で仕事しつつ心地よく五感が刺激されているのだろう。

「天神山のアトリエの内側・外側には多様な情景が生じ、想像を超えたドラマが展開する。室内には屋外の開放感とは違う快適性、物理的・心理的に守られた場所から外に繋がる心地よさのようなものがあります。地球の動きに伴い、この世界にはどこにでもダイナミックに変化し続ける環境が存在しています。それは複雑で、厳しくも、儚く美しい。そういう大きな流れに身をゆだねながら、小さな微差を愛でて、一瞬一瞬に感動できる建築をつくりたい。それを試みるために建てたのがこのアトリエです」と藤野氏は語る。

藤野氏は独立し天神山のアトリエを形にするまでに、建物を通して、環境と人はどのように連続すべきか考えるきっかけとなるような経験をしている。清水建設に勤務していた当時には、東京・銀座にある黒川紀章設計の中銀カプセルタワービル(1972年築)に住んでいた。カプセルの丸窓を通して、ジャン・ヌーベル設計の巨大なオフィスビルが、日に日に立ち上がってゆく都市のダイナミズムを目の当たりにし、メタボリズムの思想を謳いながら新陳代謝することのなかったカプセルタワーをリノベーションし、大きな都市環境と住空間を繋ぐ案をスケッチし続けたという。その後、福島・南会津のはりゅうウッドスタジオに転職してからは、移動可能な小屋をセルフビルドし、季節によって場所を移しながら暮らした。電気は外部の建物から延長コードで引き込んでいたため、一旦プラグが外れれば、極寒の冬でも、外気同然の温度で寝る経験をした。「外で野生動物が歩いているのが分かるほどの華奢な小屋だ。自分と建物の神経がつながっているような気がした」と藤野氏は思い返す。