【第158回】被覆こそ建築である~新刊「近代建築史論:ゼムパーの被覆/様式からの考察」を巡って

第158回に登壇した建築史家・川向正人氏は刊行されて間もない著書を下敷きに、21世紀になって明確に形をとり始めた、衣服のように軽く、柔らかく人を包み込むものとしての“建築の被覆”について語った。川向氏の著書(中央公論美術出版、2017年4月刊)は、19世紀ドイツの建築家、ゴットフリート・ゼムパー(1803-79)の研究を通して、彼の被覆と様式に関する思想をひもといたものだ。ゼムパーは大著『様式』(1860-63)のほか『建築の四要素』(1851)、『科学・産業・芸術』(1852)などの建築書で名を馳せた人物である。
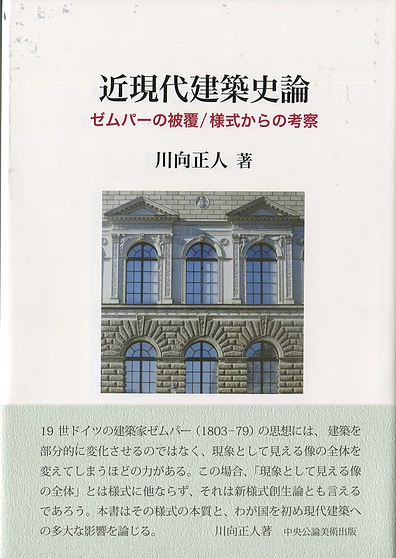
著書、表紙写真はゼムパー設計のドレスデン絵画館(部分)
ゼムパーが建築に目覚めるのは1830年前後のパリで、七月革命の頃だった。当時の多くの芸術家・建築家たちと同様に、彼もまた若い頃から社会の変革に燃えて、新しい時代にふさわしい建築のあり方を探るようになっていた。世界・民族・歴史とつながり、それを体現するような建築のあり方であって、根底にあるのは、建築によって社会を変革するという思想だった。当時、人類史の中で建築が最も完成されたのは古代ギリシアだと考えられていたが、現地に足を運び、建築を包む気候風土を体験し、実測や細部意匠の観察を重ねて、その上で論を立てる者は、ごくごく少数だった。若いゼムパーは、実際にギリシアにも渡り、1830年から33年まで古代建築の現地調査を決行する。その結果、古代ギリシア建築の最大の特徴は、それまで新古典主義が唱えてきた「輪郭線」と「白(=無地)」ではなく、様々な特徴が現象する境界面としてのサーフェスすなわち「被覆」と、そのサーフェスに現れる「色」にあることを発見したのである。たとえば、ギリシアのパルテノン神殿は建築本体も彫刻装飾も透明度の高い白大理石で構成されているが、創建当時は、非常に純度の高い顔料で繊細に透き通る彩色が施されていた。多彩な色を使うことで、建築が、より鮮明に気候風土、歴史文化を表現する場となっていたのである。新古典主義の核となる原理を否定する彼の主張は、この後、大変な物議を醸すことになるが、この主張が評価されて彼は30歳そこそこで、1834年に名門ドレスデン・アカデミーの建築担当教授に大抜擢された。
そして1851年にはゼムパーは、若い時に大胆にも提唱した「被覆」および「色」の主張を基本要素の一つとして組み込んだ、さらに構築性の高い建築論として『建築の四要素』を発表した。まずゼムパーは、自分で考え出したというよりも考古学や人類学の成果を総合して人類史の始原まで遡れば、「炉」、「土台」、「屋根(それを支える軸組があれば、それも含む)」、そして「囲い(被覆)」という建築の四つ基本要素が見出されると書く。そして、さらに被覆論のさらなる展開として注目すべきは、彼が壁体(Mauer)と壁面(Wand)を分けて、石や煉瓦を組積する壁体は、同種の素材・技術でつくられる「土台」に属し、一方、人間が目で見て感じ何かを読み取り、また触れれば快感となるような空間境界としての壁面は、「囲い(被覆)」に属すると捉えていることである。ゼムパーは、植物の枝・蔓や繊維などを織ったり編んだりしてつくられたものが、原始住居では人間の身体の最も近くにあって本質的要素となっていることに着目する。それらは空間を囲うものとして、柱の間に吊るされる場合も、壁体の前面に掛けられる場合もあるが、そのイメージは軽く柔らかく人を包み込む衣服に近い。このような建築の「被覆」のイメージは、ドイツ語のWand(壁面)がGewand(衣服)と同じ語根をもつということによっても支持されると、ゼムパーは言うのであった。

1834年のゼムパー(鉛筆画)、ETHゼムパー資料室蔵。
時代は下って1900年前後の建築被覆の例として、川向氏はオットー・ヴァーグナー設計の「マジョリカハウス」と「ウィーン郵便貯金局」を挙げる。前者は外壁をバラ模様のマジョリカタイルが覆い、有機的で植物のもつ生命を感じさせ、かたや後者は大理石やアルミニウムや黒ガラスが被覆に使われて、機械的で切れ味のあるシャープな印象をもつ。つまり、建築躯体を保護するという単純な目的に留まらず、その時代性や場所性、あるいは人と環境との関係性を表現するものであるがゆえに、被覆/様式が、このように大きく異なってくるのである。
これらの例を見ても分かるように、被覆に用いられる素材の色・寸法・隙間のあけ方などで、その建築の透明感や軽やかさに加えて周辺環境や道行く人々に対する親和・非親和の印象すら大きく変化する。ゼムパーはこうした被覆を巡る技術を「Tektonik(テクトニク)」と呼び、それを使えば建築はもう一度宇宙との関係すら回復できるとも主張した。

全体の印象を決定する被覆の重要性を示すために、川向氏はここで、春先の野山の写真を示して、木々に芽が出て若葉が茂り骨格となる幹や枝を緑が覆い、さらに木々の緑が微妙にニュアンスを変えながら山全体を覆うことによって、どれほど美しく、心浮き立つ景観が現出するかを語る。また、野原一面を黄色のタンポポが覆う写真とその全てのタンポポが黄色の花弁という被覆を失い、小さな坊主頭のような軸部だけが乱立する写真を並べて示し、自然界における緑や黄色の「被覆」の現れがいかに私たちに大きな喜びを与えているかを論じた。建築も、単体や群として機能を果たす他に、私たちの生きる環境として、まさに「被覆」を通して複雑な役割を演じていることを強調するのである。
プリニウスの『博物誌』によれば、当時被覆に使われた色の顔料は、海や山の岩石や植物などから採取されたもので、この顔料によっても建築は様々な地域と結びついていた。このことの重要性にも、ゼムパーは事あるごとに触れているという。
被覆(衣服)と自然素材と色に関連して、川向氏は人間国宝の染織作家、志村ふくみ氏の「白のままでは生きられない」という言葉を紹介した。彼女の「人間が生きていくうえでどれをとっても色があり、使う材料はすべて自然からいただくもの」「私たちは命をまとう。植物、動物の命をもらって身に着ける。私たちが着るものは“命”」をいう言葉を紹介。被覆は建築のもつ文化性、精神性を深めるための手段であって、志村氏の言葉と創作の姿勢が大いに参考になるのではないかと、川向氏は言う。
私たちは、多様な要素の集合としての建築に、色という“言葉”を用いて深い思いを込めることができる。誤解している人々もいるが、被覆/様式への着目は、志村氏がそうであるように、命や親和力の大切さを思い起こし、精神性を深めることを願うものだ。だから、こちらが一方的に使いたいと望むのではなく、素材や色の声に耳を傾け、最も相応しいところに使わねばならない。その結果として一つの望ましい世界(建築)が立ち現われることがゼムパーの被覆/様式論の原点だと、川向氏は結んだ。





