【第154回】「SEXY TECHNOLOGY -PROGRAM-SIDE OUT-」
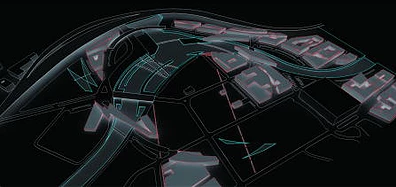
建築家フォーラム第154回は、関西を拠点としつつ、世界を舞台に活躍する建築家、そして教育者でもある山口隆氏の登壇だ。彼は「建築とは何か」といった建築論的な問題意識を持って、ひとつひとつの作品に向き合う。静謐なガラスの建築から始まり、近年では建築に生物的アルゴリズムやロボットテクノロジーを組み込むなど、新たな建築の可能性-イノベーション-を模索し続けている。大学教育の場面においても、コロンビア大学などの海外の大学とのワークショップを通じて、建築と異なる分野のテクノロジーを取り入れた設計に取り組んでいる。
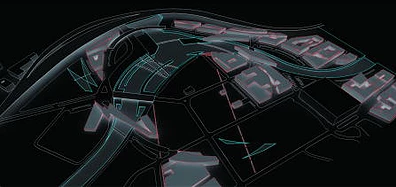
山口氏は京都大学工学部建築学科卒業後、安藤忠雄に師事し、その後独立。1988年にはコロンビア大学院出身者やピーター・アイゼンマンのパートナーらと研究グループARXを結成し、「建築における主体の解体」という理論を構築した。その後、ニューヨークとベルリン、リスボン、日本を結び、ネットワーク上での設計活動を開始。複数の主体がテレコミュニケーショナルに相互干渉する設計手法で、1992年頃、「主体の解体」の理論を具現化した。FAXでリレーして次々と設計を発展させていくアプローチが面白かった、と当時を振り返る。
若くして、安藤忠雄とアイゼンマンというふたりの建築の天才と関わりを持つという垂涎の環境だが、直感的に形をつくり上げていく安藤忠雄と、理論的に建築の歴史を塗り替えるアイゼンマンの方法論の「板挟みに苦しんだ」という。また、安藤忠雄は自らが主体的に設計するのに対し、アイゼンマンは自らの意思を離れ客観的に設計を行う。建築へのアプローチは正反対である。とはいえ、この手法の双方が原点であり、1992年頃から山口氏の中で融合し始めていると説明する。
今、山口氏は、欧米と比べて日本はイノベーションが起きにくいことを痛感している。誰もがリスクヘッジを最優先して冒険しない。技術者はひとつの技術を内向きに突き詰めようとはするが、壮大な理念に向かって従来のやり方を脱皮するような挑戦はまずしない。
ザハ・ハディドの設計した新国立競技場が実現しなかったのも、日本にイノベーションの精神がないからだと言う。日本は水平・垂直の「墓石ビルディング」に、コストを調整しながら、必要十分な機能を収めるという既存の技術を正確にこなすことは得意だ。しかし、ザハの描いたような独特な曲線は、技術的にも、コスト的にも可能性を読みにくかったのではないか。解決に向け新しい技術を取り入れることに、とまどいがあったようにも感じられるという。
今、山口氏は建築の「悉皆屋」を目指している、と話す。悉皆屋は着物を仕上げるための40近い工程に関わる職人たちを束ねる職業だ。それぞれの職人は、先に述べた技術者と同じく自分の仕事を全うし冒険はしない。そうした職人=技術者を束ねることで、大きなイノベーションを起こそうとするのだ。ひとつだけでなく、複数の異なる分野の技術者が交流すればイノベーションの可能性はさらに高まる。
今回のフォーラムには、テーマの「SEXY TECHNOLOGY」が示す通り“挑発的な”意味があった。山口氏は、工学系のテクノロジーは単に目の前の問題を解決するものであり、それを越えて、もっと“挑発的に”先の状況を生み出すべき視点が必要と理解しているからだ。Architectureとは「アルケー=根源」と「テクネ=技」から成る言葉。Architectureの原点に立ち戻り、さまざまなテクノロジーを取り入れながら、根源的な部分から思考するのが建築のイノベーションに繋がるのではないか、と山口氏は言う。日本人の持つ器用さで、外部から得たテクノロジーをそのまま模倣し、表層的な部分のみ変化させてきた従来のやり方を、そろそろ再考するときがきたようだ。





